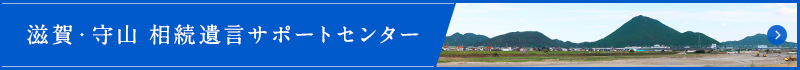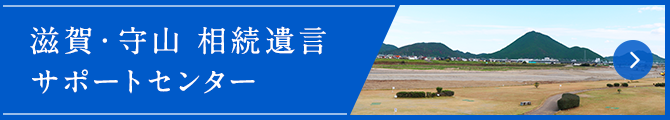相続・遺言相談SERVICE
TOP > 相続・遺言相談
相続発生前

- 遺言書作成
-
相続財産の配分をめぐり、それまで仲の良かった相続人の間で争いが起こることが少なくないため、遺言書を作成することで相続人同士の争い を未然に防ぐことが必要です。
あいリーガルでは、お客様の意思を尊重した相続を行なうために、遺言書作成のサポート、遺言執行者への就任を承っております。 - 遺言書の種類
- 代表的なものとして以下の2種類があります。
公正証書遺言
証人2人が立ち会い、公証人に口頭で述べた遺言の趣旨に基づいて公証人が作成する遺言書です。
専門家が作成し、なおかつ原本が公証役場で保管されるため、最も確実な遺言といえます。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で全文記述した遺言書です。書式は自由ですが、パソコンや自筆のコピーは認められません。
日付の記入と署名、押印が必要です。遺言書の紛失、偽造や形式不備で遺言自体が無効となるリスクがあるので注意が必要です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、あいリーガルでは最も安全で効果も確実な公正証書遺言の作成をお勧めしております。
遺言書の作成には、遺留分や相続税の問題、各種書類に関する専門的な知識が必要になります。
お客様のご要望をお聞きしながらアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 - 生前贈与
-
あいリーガルでは、不動産を生前贈与する際に必要となる名義変更等の手続きをサポートしております。
生前贈与は相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いの防止や、相続税対策に遺産総額を下げるのに非常に有効な方法の一つです。
生前贈与の際に利用できる主な制度
基礎控除:贈与税は年間110万円の基礎控除が認められています。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
配偶者控除:婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の授与が行なわれた場合、基礎控除の110万円の他に、最高2,000万円まで控除できます。
相続時清算課税制度:原則65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与した場合に2,500万円までであれば非課税となる制度です。但し、贈与した財産は、贈与者が亡くなった際、相続財産として含めて相続税を計算することになります。 - 相続対策丸ごとサービス(生前相続対策業務)
- 相続が発生すると、親しい方を亡くした大変な状況の中で、各種の手続きや場合によっては相続税の納付など多くのことに対応しなくてはなりません。また、遺産を巡る争いが生じる可能性もあるため、円満な相続に向けて、元気なうちにできることをお手伝いさせていただきます。
- 民事信託
- 民事信託の特徴は何といっても、「それぞれのご家族に合った財産管理や遺産継承、オーダーメイドで柔軟な資産継承の形」をつくれる点です。詳細はお気軽にお問い合わせください。 争いが生じる可能性もあるため、円満な相続に向けて、元気なうちにできることをお手伝いさせていただきます。
相続発生後

- 遺産相続手続
- ※一般的な遺産相続手続きの流れは下記の通りです。
あいリーガルでは、書類の作成、登記申請から、ご希望であれば書類の収集等も全て行います。 - 遺産相続の流れ
| 相続人調査 (戸籍謄本の収集、相関関係図作成) |
まず最初に相続人調査に取りかかります。具体的には戸籍謄本収集と相続関係図の作成が必要です。 調査にあたっては亡くなった方と法定相続人全員の戸籍謄本等を集め、関係者全員の相続関係説明図を作成します。 |
|---|---|
| 相続財産調査 (不動産、預貯金、有価証券等の調査) |
土地や建物等の不動産調査や預貯金の調査が必要ですが、特に預貯金は早めに進める必要があります。 また有価証券をお持ちの場合は相続開始時での評価を出します。 |
| 相続方法の決定 (単純相続、限定承認、相続放棄) |
相続開始から3ヶ月以内に、誰がどの程度の財産を相続するか、放棄するか、一部だけ相続するかを決めなくてはいけません。 決め方については、法定相続人同士で電話や手紙などで話がついていれば大丈夫です。 |
| 遺産分割協議 (遺産分割協議書の作成) |
相続人や財産の調査が終了し、財産目録を作成した後は遺産分割協議となります。 ここでは相続人全員での協議を行い、遺産分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。 |
| 財産の名義変更 (不動産、預貯金の名義変更) |
遺産分割協議書がまとまった後、遺産相続手続き先の所定の用紙や遺産分割協議書に戸籍謄本等によって判断された法定相続人全員の署名と実印をもらい、必要な戸籍謄本等や印鑑証明を添付して、各手続き先機関に財産の名義変更を行います。 不動産の場合は法務局に所有権移転の登記申請を行い、預貯金は各金融機関で申請します。 |
- 相続登記
- 故人の不動産を引き継いだ場合、不動産の名義を変更する手続きが必要になります。 これを「相続登記」といいます。この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。また2024年(令和6年)4月からは相続登記が義務化となり、一定期間内に登記をしないと過料が科される可能性があります。
- 相続放棄
- 相続放棄は、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、対象となる財産や借金の一切を「相続しません」と宣言し相続を回避することです。これにより借金を引き継がないこととすることができますが、相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所にて手続きをする必要がありますので、ご検討中の方は早めにご相談ください。
- 相続手続き丸ごとサービス(遺産整理業務)
- 遺産整理業務は、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口になり、不動産・預貯金の名義変更や戸籍謄本の取得など発生する煩雑な手続きをすべて一括でお引き受けするサービスです。
各種手続きの注意点
『 ご自身で相続手続きをされるとこんなに大変です 』

遺産の相続や遺言などで
もめる可能性があります
遺産相続や遺言の取り扱いを誤ってしまうと、相続人間での争いに発展しかねません。感情的な衝突を避け、落とし所を見つけるためには正しい法的知識・対応が不可欠です。場合によっては、親族間での関係性が損なわれた後戻らない可能性もあるため、どのような問題点が予期されるか等を考慮し、慎重に進めていく必要があります。

煩雑な手続や法律の知識が必須です
相続が発生すると、不動産・預貯金などの名義変更や年金手続きを行うために、役所・保険会社・金融機関・水道やガス等の公共サービス・勤務先など非常に多岐に渡る関係各所への連絡とそれぞれの手続きが必要になります。すべての手続きを滞りなく完了させることは非常に困難なため、精通している専門家にお任せいただければと思います。

期間に制約がある
手続きがあります
不動産登記については法改正により2024年(令和6年)4月からは3年以内に相続登記が義務化されます。また、相続放棄は相続発生を知ったときから3ヶ月以内にする必要があったり、相続税申告は相続発生から10ヶ月以内にする必要があるなど、手続きの期間が定められている手続きがあります。これらの手続きを期間内に行うため、専門家としてスピーディーに対応させていただきます。
『 専門家にご相談されるメリット 』
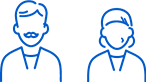
相続トラブル予防がしやすくなります
相続による骨肉の争いを予防し、感情的な衝突を避けるためには、第三者の専門家のサポートが重要です。正しい法的対応によって、ご家族・ご親族の対立予防に貢献させて頂きます。何十種類にも及ぶ相続手続きから、お客様に合った正確な方法によってきめ細かな支援をさせて頂きます。

法律の専門知識が必要な手続きが
スムーズに進みます
税金のお支払いのほか、役所や金融機関などに通う必要のある、専門的な手続きを代行させていただきます。他士業など様々な分野のプロとも連携しておりますので、あいリーガルを窓口にスムーズな対応が可能です。

相続手続きに使う時間や手間が
大幅に減ります
平日日中でないとできない手続きや、大勢の相続人との話し合いを代行させて頂きますので、お仕事を休んだり多くの相続人を訪ねたりする時間や労力の負担が大幅に軽減されます。

地域の専門家ネットワークによるワンストップ対応
弁護士や税理士など他の法律家のみならず、不動産業者や遺産整理業者など様々な専門家と連携し、あいリーガルを窓口としたワンストップ体制で親身に対応させて頂きます。
-

相続税等の手続き
税理士 -

紛争等の解決
弁護士 -

年金等の手続き
社労士 -

不動産の売却
不動産業者 -

遺品の処分
遺産整理業者
相続における代行業務の例
- 戸籍収集(戸籍調査や取得代行など)
- 相続関係説明図の作成
- 財産目録(財産の一覧表)の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 相続放棄の申し立て
- 不動産の相続に関する登記(名義変更)
内容によっては弁護士や金融機関に依頼されるより費用が安くなる場合があります。
お見積もりは無料ですので、詳細のお気軽にご相談ください。
主な費用一覧
いずれも税込価格ですが実費は別です
相続人調査確定・法定相続情報証明取得
| 戸籍収集(5通まで) | 11,000円〜 |
|---|---|
| 戸籍等追加収集 | 1通あたり2,200円 |
| 相続関係説明図作成 | 13,200円 |
| 法定相続情報取得 | 22,000円 |
遺産分割協議書作成
※相続人は人数や状況に応じて、別途費用をいただく場合がございます。
| 遺産分割協議書作成 | 22,000円〜 |
|---|
相続登記・名義変更手続き
※不動産の物件数、評価額、収集する戸籍の通数、相続人の数などにより料金に変更が生ずる場合がございます。
| 項目 | 相続手続ライト | 相続手続スタンダード | 相続手続プレミアム |
|---|---|---|---|
| 相続ご相談・アドバイス | ○ | ○ | ○ |
| 相続登記(申請・回収含む) | ○ | ○ | ○ |
| 相続関係説明図作成 | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | ○ |
| 被相続人および 相続人全員分の戸籍・評価証明書取得 |
ー | ○ | ○ |
| 預貯金・動産等の払い戻し・名義変更 | ー | ー | ○ |
| ●合計金額の目安 | ※77,000円 | 99,000円 | 143,000円 |
※遺産分割協議書作成を含まない場合は55,000円~
| 相続手続ライト | |
|---|---|
| 相続ご相談・アドバイス | ○ |
| 相続登記(申請・回収含む) | ○ |
| 相続関係説明図作成 | ○ |
| 遺産分割協議書作成 | ○ |
| 被相続人および相続人全員分の戸籍・評価証明書取得 | ー |
| 預貯金・動産等の払い戻し・名義変更 | ー |
| ●合計金額の目安※77,000円 | |
※遺産分割協議書作成を含まない場合は55,000円~
| 相続手続スタンダード | |
|---|---|
| 相続ご相談・アドバイス | ○ |
| 相続登記(申請・回収含む) | ○ |
| 相続関係説明図作成 | ○ |
| 遺産分割協議書作成 | ○ |
| 被相続人および相続人全員分の戸籍・評価証明書取得 | ○ |
| 預貯金・動産等の払い戻し・名義変更 | ー |
| ●合計金額の目安99,000円〜 | |
| 相続手続プレミアム | |
|---|---|
| 相続ご相談・アドバイス | ○ |
| 相続登記(申請・回収含む) | ○ |
| 相続関係説明図作成 | ○ |
| 遺産分割協議書作成 | ○ |
| 被相続人および相続人全員分の戸籍・評価証明書取得 | ○ |
| 預貯金・動産等の払い戻し・名義変更 | ○ |
| ●合計金額の目安143,000円 | |
| 預貯金の払い戻し(残高証明書取得を含む) | 44,000円〜/件 |
|---|
遺言関連
| 遺言書作成(自筆証書) | 44,000円〜 |
|---|---|
| 法務局への遺言書保管申出(同行含む) | 33,000円~/件 |
| 遺言書作成(公正証書) | 55,000円〜 |
| 証人立会い | 11,000円/名 |
- 遺言書作成(自筆証書)
- 44,000円〜
- 遺言書作成(公正証書)
- 55,000円〜
- 証人立会い
- 11,000円/名
遺産整理業務・遺言執行費用(定率部分)
※定額報酬として財産の承継人等一人当たり5万円掛かります。
※受託事務処理内容によって、依頼者との合意の上報酬が変動する可能性があります。
| 遺産額500万円以下 | 26万5千円 |
|---|---|
| 遺産額500万円以上5000万円以下 | 価格の1.2%+20万9千円 |
| 遺産額5000万円以上1億円以下 | 価格の1.0%+31万9千円 |
| 遺産額1億円以上3億円以下 | 価格の0.7%+64万9千円 |
| 遺産額3億円以上 | 価格の0.4%+163万9千円 |
- 遺産額500万円以下
- 26万5千円
- 遺産額500万円以上5000万円以下
- 価格の1.2%+20万9千円
- 遺産額5000万円以上1億円以下
- 価格の1.0%+31万9千円
- 遺産額1億円以上3億円以下
- 価格の0.7%+64万9千円
- 遺産額3億円以上
- 価格の0.4%+163万9千円
生前贈与
| 生前贈与登記 | 38,500円〜 |
|---|---|
| 贈与契約書 | 16,500円〜 |
- 生前贈与登記
- 38,500円〜
- 贈与契約書
- 16,500円〜
裁判書類作成
| 相続放棄 | 44,000円〜/名 |
|---|---|
| 遺言書の検認申立(検認時への同行もいたします) | 55,000円〜 |
| 遺言執行者の選任 | 44,000円〜 |
| 特別代理人選任申立 | 44,000円〜 |
| 成年後見申立(裁判所への同行もいたします) | 110,000円〜 |
必要書類作成
| 戸籍収集一式 | 11,000円〜 |
|---|---|
| 各種証明書(所在地の市町村役場) | 1,100円〜/通 |
| 残高証明(金融機関) | 11,000円〜/回 |
- 戸籍収集一式
- 11,000円〜
- 各種証明書(所在地の市町村役場)
- 1,100円〜/通
- 残高証明(金融機関)
- 11,000円〜/回
主な解決事例
相続人の方が現地にいらっしゃらない。
亡くなられた方が守山にお住まいだったが、ご子息が関東在住。手続きのために休みを取って帰省しにくいので専門家に依頼したい。
兄弟が立て続けに亡くなってしまった。
兄弟で守山に居住していたが、先に片方が亡くなった時点で、 感情面や体調などを含め何も進められないような状態に陥ってしまっていた。 そこで葬儀の段取りから全て対応を依頼したい。
自筆の遺言を遺してもらったが、どうしたらいいのか分からない。
亡くなった父に昔借金があったようで心配している。
子どもがいないので妻に遺言書を遺したい。
前妻との間に子どもがいるので遺言書を遺したい。
内縁の妻に遺言書を遺したい。
子どものうちの一人に財産を遺したくない。
よくあるご質問
- 実家が遠隔地ですが、相続登記の手続きはできますか?
- 大丈夫です。不動産を管轄する法務局へ登記申請を行うのですが、郵送やオンラインでの申請に対応しておりますので、 実際にお会いすることなく相続登記を進めることが 可能です。戸籍等の取り寄せもお任せください。
- 相続はいつまでにしなければならないのですか?
- 相続登記は2024年(令和6年)4月から義務化されますので、ゆくゆく問題にならないように相続人間の話し合いがまとまるうちに進め完了させることが望ましいです。 また、相続放棄は自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に申請する必要があったり、相続税の申告は相続発生後10ヶ月以内にする必要があったりと、期間の制限がある手続きがありますので、ご心配な方は一度ご相談ください。